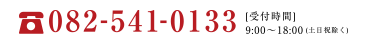〒730-0053
広島市中区東千田町2-3-26
リハビリ工法協会 事務局
Mail : info@j-cma.jp
広島市中区東千田町2-3-26
リハビリ工法協会 事務局
Mail : info@j-cma.jp
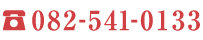
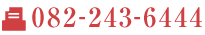
コンクリート構造物の補修技術
1.はじめに
コンクリートは安価で優れた構造材料としてあらゆる社会資本の根幹を成すものであるが、それら多くのコンクリート構造物は既に高齢化が進んでいるのが現状である。これらの老朽化したコンクリート構造物を全て更新することは経済的に困難であり、適切な維持管理を行うことによって構造物の長寿命化、延命化を図ることが急務である。適切な維持管理とは、コンクリート構造物の点検、調査、診断、補修、補強、モニタリングなど多岐にわたる。適切な調査、診断を行うためにはコンリートの劣化機構とそのメカニズムを理解することが不可欠であるとともに、それらを定量的に評価するための非破壊検査手法や分析方法の知識も求められる。そうした適切な調査、診断の結果が得られてはじめて適切な補修、補強へと進むことができる。そして調査、診断、補修、補強の技術は常に進化し続けており、新しい技術、材料、工法は次々と生み出され、実用化されている。維持管理分野における新たな知見を反映するために、2013 年には土木学会のコンクリート標準示方書[維持管理編]が改訂されている。コンクリート工学会では、コンクリートの維持管理分野の重要性を鑑み、「コンクリート診断士」制度を推進しており、既に10,000 人を超えるコンクリート診断士が日本全国で活躍している。維持管理分野の適切な知識と技術を有する技術者が、常に新しい知見を吸収し、活躍することによってのみ、既設コンクリート構造物の長寿命化、延命化が図られるのである。持続可能な社会の形成。これこそが今後我々が進むべき将来像である。
このような状況の中、この度一般社団法人コンクリートメンテナンス協会の技術資料が改訂されることとなった。主な内容は当協会が取り組んできたコンクリート構造物の維持管理技術のうち、特に「コンクリートの塩害、中性化、アルカリシリカ反応(ASR)」と「亜硝酸
リチウムを用いたコンクリート補修工法」に主眼を置いてとりまとめたものであるが、前述の通り新たな知見と技術の進歩を反映させた内容となっている。今後のコンクリート構造物の適切な維持管理において、本書が有効に活用されれば幸いである。
広島工業大学工学部
教授 十河茂幸
教授 十河茂幸
私たちコンクリートメンテナンス協会は1999 年に広島県で発足いたしました。広島県は沿岸部では海砂、山間部では融雪剤による塩害、そして全県でASR の発生がみられるなど、コンクリート劣化が多い(激しい)地域です。補修に取り組み始めたころは失敗の連続でした。しかし、劣化の原因を分析する事で徐々に安全で確実な補修方法が分かるようになってき
ました。
コンクリート補修は決して難しいことではありません。調査から補修設計そして補修工事と、筋書を作りトータルで考える事が大切なのです。 コンクリート補修を行うとき、まず現地で調査して劣化原因と劣化因子の特定をします。それは、塩害なのか、中性化なのか、ASR なのか?次に、症状のグレード、潜伏期、進展期、加速期、劣化期のどこに位置するのかを確認します。そのためには、その数値的裏付けの判断基準が必要です。塩害だと塩分量、中性化だと中性化残り、ASR だと残存膨張量などです。それから、求められる補修結果の要素を加える、それは、置かれた気象的環境、経済的環境、構造物の重要度、延命期間などです。そして最後に補修方法の決定という筋書に沿(そ)って進めばいいのです。
補修工法には二つの考え方があります。今後、劣化因子を入れない補修方法なのか?それとも、既に劣化因子が一定以上入ったものの補修方法なのか?の二つです。劣化因子を入れない方法は、環境に応じて、要求される性能を考慮して、被覆材を選択すればいいと思います。次に、劣化因子がすでに入ったコンクリートの補修ですが、一見すると難しそうに感じますが、実は選択肢はそんなに多くありません。塩害・中性化による劣化ですと、鉄筋防錆を目的とした工法になります。鉄筋防錆を目的とした工法は、防錆剤を使った工法か電気防食になります。防錆剤を使った工法の代表格が、亜硝酸イオンを使った工法です。また、ASR だとリチウムイオンを効果的に内部圧入する工法でしか化学的には劣化の進行を止められないのです。
このようなシナリオで考えを進めていけば、コンクリート補修は決して難しいものではないのです。
2006 年から、「コンクリート構造物の補修補強に関するフォーラム」と題しまして、毎年講習会を開催してきました。2014 年は全国23 か所で開催し、3500 人を超える参加者が受講しており、コンクリート補修への関心が年々高まっているのを感じています。
本書が、コンクリート補修に取り組む皆様のお役に立つことを祈念しております。
一般社団法人コンクリートメンテナンス協会
会長 徳納 剛
会長 徳納 剛
Copyright(C) 2009〜 リハビリ工法協会 All rights reserved.